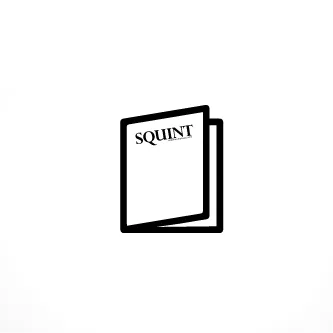SQUINT
COLUMN #4

白山眼鏡店を愛用する人たちの、眼鏡のお話。
第四回目は、作家の岩下尚史さんが登場です。
Photo: Shiori Ikeno
修正改良
色々と不平の多い私だが、就中最も気に入らないのは自分の顏である。
どこがどう不滿であるかを書くと、これを読んだ人が私を見たときに、そこばかりに注目する惧れがあるから、敢て伏せることにするが、どこもかしこも違和だらけなのは、兩親が勝手に造ったのだから爲方がない。
これに修正を加えたいならば整形手術をすればよろしいと勧める人もあるが、直したあとで思いが違ったり、亦、首尾能く適ったとしても保全のためには繰り返して針を入れる必要もある。憚りながら准富裕層の私にとって、その費用など可怕くはないが、顏に幾度も針を刺されるのは恐ろしい。
そんな私が五十の坂を越した頃、歌舞伎や歌劇へ行くたびに目前の舞台がぼやけはじめ、書斎で文読む際にも字が重なって頭が重くなると云う、これまで知らなかった差閊えが起りはじめた。
顏かたちは不良だが眼と齒だけは良品に産みつけて呉れたおかげで、少年の頃から眼鏡知らずであった私だが、某日、青山の隠田あたりを散策中に、いかにも商賣氣の無さそうな眼鏡舖を見掛け、ついと扉を押したのが今から十年ばかり前であったとおぼえる。
何とはなしに深沈な氣を湛える店の棚には、いづれを菖蒲燕子花、イキに走らず野暮にも堕さぬ眼鏡枠の数々が客の好みに應じて一ト目で撰擇出來るよう、それぞれ同趣向のものを一括にしながら、鹽梅よろしく飾られていた。少なくとも私には然うであったから、迷うことなく是れと思う品の色違いを三種ばかり、係りの人に取らせて顏に合わせることにした。
すると驚いたのは、鏡の中の私の顏が、かねがね私が思っていたとおりの、私の顏になっていたことである。あたりまえじゃないかと嗤うのは仕合せな人で、私は鏡を覗くたびに、自分の思う自分の顏ではないことに憮然として、長い年月を暮らして來たのである。
ひとしおの御機嫌にて、膚の色に照らして色を撰び、奥の一室で視力を詳細に吟味した上でレンズが極まり、幾日か待って私のものになった人生初の眼鏡は掛けても何の違和感もなく、私の顔そのものであった。
これで、長年の懸案であった美容整形手術の手間は、一と先ず、なくなったのである。
それから三年ばかりして、飽きたのではないが、もう一つ、眼鏡を誂えたくなって上野の本店を訪れた。同じものをと思ったが、ひとふし異なる品で惹かれるものがあったから、試みに顏に合わせてみた。
不思議なことに、今のものより、しっくりと納まった。係りの人が視力を吟味すると、老眼も進んでいたので、枠もレンズも新規なものをあつらえた。私にとって眼鏡は道具ではなく、年々歳歳、共に生きては變化する生身の一部となっている。
こうして三年ごとに、同じようで同じではない眼鏡を作っているが、周囲の人たちは變へたことに氣が付かないらしいのは、私に無關心であるのか、眼鏡が私の顏そのものと化している爲かは分からないが、結果が宜ければ構いはしない。
さて、流行らない作家である私は、文筆だけでは贅澤が出來ないから、講演會や放送局に出向いては無駄ばなしをして稼ぐと云う惡い癖が付いた。
そんなことをしていると、未知の人たちから様々な便りが届くが、貴殿の眼鏡はどちらの御品ですか、と云うのも珍しくはない。
ところが、私の買い付けの眼鏡舖は、名聲赫赫たる著名人を顧客に持ち、趣味の好さでは定評があると聞いている。
はい、白山眼鏡ですよ、と私が應じたならば營業妨害になると思い、これまでは馬耳東風で通して來たが、先方から文章の注文が來たくらいだから、迷惑ではなかったらしい。これからは、こっそり、教えてあげようと思う。
PROFILE
岩下尚史
1961年生。作家、國學院大學客員敎授。
新橋演舞場、シス・カンパニーを經て著した初作『芸者論』が和辻哲郎文化賞を受賞。
他に『ヒタメン‐三島由紀夫、若き日の恋』『大人のお作法』等。