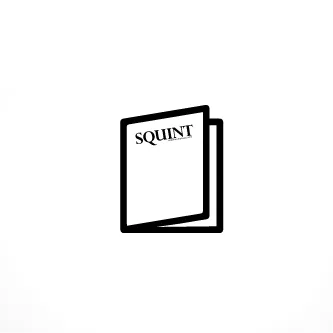SQUINT
LINKS #1
さよならだけが人生だ、と言うけれど、やっぱり別れは辛いもの。できることなら、これからをずっと共にしていけるような人と、物と手を取り合って、僕らは楽しく暮らしたい。白山眼鏡店と、ゆかりの人々とが花を咲かせる四方山話。第一回目のゲストはスタイリストの草分け、北村勝彦さん。あの日の出会いと、その先にあった今を結ぶいくつかのエピソード。彼らが見つけた、絆の形。
photo: Kousuke Matsuki text: Rui Konno translate: Koharu Tada

ホスト:白山將視

北村勝彦
―お2人は初めて会ったときのことは覚えていますか?
白山將視(以下白山): 覚えてますよ。’79年に出したウチのカタログで北村さんにスタイリングをしてもらったんですけど、知り合ったのはさらに2年くらい前でした。僕は’75年から眼鏡を自分で作るようになったんですけど、北村さんはそれをすごく面白がってくれて、自分でも使いながら『POPEYE 』に載せてくれて。
北村勝彦(以下北村): 確か『an・an』で取り上げられてたのを見て、白山の眼鏡が気になったのが最初だったと思う。白山眼鏡ではヨーロッパ系の手に入りにくいサングラスやフレームが置いてあったよね。
1番印象的だったのは「EMMANUELLE KHANH(エマニュエル・カーン)」。あとは映画の『8 1/2 』でマルチェロ・マストロヤンニが掛けてた「Persol(ペルソール)」の”RATTI(ラッティ)”とか。
―それが雑誌に載ったのだから、反響も大きそうですね。
北村:それはもうリアクションどころの問題ではなかったよね。大騒ぎになったこともあるし。
白山:北村さんが最初に“POP EYE ”っていうコーナーでこのボストン型を紹介してくれたんです。“白山っていうところがイギリスで面白い眼鏡を見つけて輸入したぞ”っていうような。そしたらそれを見た人たちから、ウチに電話が400 、500くらいかかってきて。それがメガネにまつわる最初の動きと言っていいほどの異常な反響でした。
北村:それで問い合わせの電話をかけてきたヤツとすったもんだやった記憶がある。「ジョン・デンバーが掛けているのがそれだ!」と言って、頑として聞かないんだよ。それはまた別のモデルなんだけど、「いや、あなたが載せたものがジョン・デンバーの使っているやつだ」って言って。
白山:そうですよね。あれは多分「American Optical 」ですよね。だけど、当時はボストン型っていうだけでジョン・デンバーのだ!ってなっちゃう時代だったんですよね。
―スタイリストの北村さんが直接読者の問い合わせを受けていたんですか?
北村:昔はね。タイトル付けから原稿からページ構成まで全部その人がやらなきゃいけなくて、担当者の名前を入れるっていうのが『POPEYE 』の基本方針だったから。毎号ハガキが編集部に段ボールで4、5箱くらい送られてきていて、全部に目を通してたよ。何十年も経って驚いたのは、編集会議を1回もやったことがなかったこと。夜、馬鹿話をしていてその中から企画のネタを拾っていくわけ。だから当時の編集部は毎日が不夜城だった。電気が消えたことがなかったね。
―どこから仕事でどこからオフかがわからないですね。
白山:遊んでいると思っているときが仕事だったりしましたよね。
北村:当時は木滑(良久)さんが編集長で、副編集長が(石川)次郎さんだったんだけど、“遊べ”というのが木滑さんの持論で。夜遊びでも何でもOK 、人様に迷惑をかけない限りはとにかく遊べ、遊ばないと良い編集者にはなれないって、そういう考え方の人だった。
白山:情報を得る道がほとんどリアルな体験からだった時代ですしね。
北村:当時はアメ横とかに行って色々と物色してたんだけど、そういうことがもう無くなってきちゃったんだろうね。昔、何かの雑誌でジャンニ・ヴェルサーチがラコステのポロシャツを着ていて。それを見て懐かしくなって、アメ横には絶対あると思って行ったの。でもアメ横はもうしまっちゃってたんだよね。ブームがとっくに去っていて、売り物にならないから。(当時『POPEYE 』の編集者だった)松山猛と俺が行って、「見せてくれ」って言ったら裏に結構な数があって、いくらかと聞いたら1000円とか1200円とか、破格の値段だったんだよね。あっちからしたら“なんで今さらラコステを?”って思ってたと思う。それを『POPEYE 』でそんな値段で紹介したら火がついちゃって、店の人にどやされた。

―読者の方からしたら迷わず“買い”でしょうね(笑)。
北村:それがきっかけでワンポイントものは復活するんだけど、後々俺が知り合いのフライトアテンダントの人に、「ジャンニ・ヴェルサーチが着ていたものが本当にラコステか確認してほしい」と言って、「もしその雑誌が手に入るようだったら買ってきてくれないか」とお願いしたら、すごい苦労したようだけど持ってきてくれて。で、カラーだったんだよね、その写真が。そしたら黒のラコステだったの。当時黒のラコステなんてほとんどなかったから、猛も「さすがヴェルサーチだな」って。それで、そのフライトアテンダントにまた「黒を買ってきてくれ」と頼んだりして。ぼくらの時代って、手に入れたい物ってそういう存在だったんだよね。足を運ばなきゃいけなかったけど、探す楽しさがあった。だけど、もう今は足を運ばなくても難なく手に入る。
幸せではあるけど、深く掘り進めていくと不幸せかもしれないね。
白山:入手しにくい時代の方が手に入ったときの喜びは大きいですよね。今はある程度のところまでイージーに辿り着けてしまうけど、不便な方が色々試行錯誤をするから。

―そういう、人と違うものが欲しいとかっていう根底にある気持ちは今も昔も共通してるかもしれませんね。
北村:いつの時代でもあると思うよ。ただ、不易流行。どんなに時代が変わっても変わらないものもあるんだよ、っていう、その良さがわからないと。今の時代の人たちにその感覚があるかどうかだよね。
それがわかってくると、ライフスタイルがちょっとだけ違う風に見えてくる。
―白山さんがメガネを仕入れていたのも、似た感覚があったんでしょうね。
白山:他と違うことをしたい、わざわざ来てもらえる魅力をお店に持たせたいという気持ちがありましたよ。日本に紹介されてない眼鏡を引っ張って来て並べる、っていうことをやりたいなって。
北村:日本でつくった洋服でコレクションをやって、向こう(海外 )で注目されたのは三宅一生さんと川久保玲さん、山本耀司さんの3人が先駆者だと思うんだけど、メガネっていうカテゴリで考えると白山のところが1番早かったと思う。先駆者だと思うよ。白山が自分のコレクションから楕円形っぽい小さなアンティークの物を僕にくれたんですけど、それがもう30年とか40年くらい前かな。
―今日は北村さんには実際に長く愛用しているものをいくつかお持ちいただきましたが、これまでには買い物の失敗も多かったんですか?
北村:たくさんありましたよ。1発目の失敗は「Brooks Brothers」。アメリカのお店でコードヴァンのペニーローファーを買ったんだけど、片足
でフィッティングだけ確認して、家に帰ったら左右のサイズが違ってた(笑)。店の間違いだけど、ちゃんと両足履かなきゃだめだな、っていう。
白山:(笑)。
北村:でも「Brooks Brothers」のその後の対応は立派だったね。
丁重に副店長が出てきて謝ってきて、「データも残っているのですぐに取り替えます」と言われて、マフラー1本もらいましたよ。それに、当時のブルックスで“この時期しか見れないな”っていうようなシーンをクリスマスに見たのよ。そういうときって、おじいちゃんからお父さん、孫までみんなが店に来て、それぞれのアンダーウエアをダースで買っていくの。これって日本にはないなぁ、素敵だなぁと思ったよ。
白山:やっぱり洋服の文化ですよね。
北村:それで、子供とか孫とかはまだ色んなチェックのものとかを選ぶけど、親とかおじいちゃんとかになると決まったカラーだけを買っていくの。いろんなものを試してきて、もう好きなものが決まっているんだよね。
―例えば今の若いスケーターたちが白の無地Tで決まったブランドの形や生地にこだわるのとも似ていますね。
北村:それはあるかもね。ただ、それが代々続いているっていうのが大事で。そこがおしゃれだよね。1代で終わらないで、しかも、そんなに高価なものじゃないからなおさら格好良い。それが高級なものだったらちょっと嫌味じゃない。男の下着を一家揃って……っていうのが良い。
白山:しつけじゃないけど、親が子供にちゃんと教えていたんでしょうね。良い物を。アメリカっていうよりイギリスっぽいですよね、そういう
伝統みたいなものって。
北村:そうだね。あぁ、なるほど。おしゃれってこういう所だよな、って思ったよ。
白山:ウチにも親子で来てくれるお客さんは結構いらっしゃいますよ。親子が違うモデルを選んだり、同じモデルでも全然違う掛け方をしてるとか。嬉しいですよね。どう取り入れるかで似合い方がまた違うんですよ。
北村:俺だったら親とは違うのを掛けるかな(笑)。
白山:基本はやっぱり、親父が格好悪いと思っていた時代でしたよね。自分が20歳とかの頃は親父はただダサいな……とかって。でも今振り返ると意外とお洒落なこともやってたんだよなぁって思います。
北村:うちの親父は職人で油まみれになる仕事だったけど、催し物とか何かのときにちょっとドレスアップしなきゃいけないときがあるじゃない? そういうときにちょっとジャケットとかスーツを着ていると、アレ?と思うときはあったよね。1番印象に残っているのでは、山登りとか渓流釣りをやっていた親父だったから、登山靴にニッカボッカ履いてツイードのジャケット着て巌の上に立っている写真があったなぁ。我々の親父の時代ってアメリカよりイギリス寄りだから、お袋が編んだ手編みのセーターとかを着ていたりして、今写真で見るとそれが結構良いんだよね(笑)。当時は気づかなかったけど。白山もそうだったと思うけど、母親が編んだセーターなんて着たくなかったじゃない?
白山:ウチはセーターとかは編んでくれない家でしたね(笑)。
北村:(笑)。でもそういう手編みの温もりとかって、やっぱり捨てられないじゃない。愛着が湧いちゃうと流行り廃りの問題じゃなくなってくる。それは買ったものにも出てくるし、それが見極めの目を養うことにもつながってくると思う。これもおしゃれの魅力なのかもしれないよね。ファッションショーとかっていうのも良いんだけど、やっぱりそこで生活している人のおしゃれが俺は好き。
白山:そこに必然性があるから格好良いんですよね。
北村:そうだね。前イギリスに行ったときに驚いたんだけど、ライっていう漁港にいるおじさんたちが、ダッフルコートの上にセーターを着てるんだよ。この着こなしは半端じゃないと思って理由を聞いたら、「俺はエビ漁をやっているから網目が細かくてトグルが引っかかっちゃう。
ニットを着ているとトグルも隠れるから引っかからないんだ」って言うの。それで、なるほどね、って。仕事とか生活とかの知恵から生まれたものってすごいよね。そういう風に培われたものっていうのはゆるぎない力を持っているから。基本はメガネも同じで、視力を補うもの。それがファッションとどこかでイコールになっていないと、嫌なんだよね。
白山:わかりますよ。道具としての機能を満たした上でのおしゃれ、っていうことですよね。物語から生まれるっていうか。
―“お洒落”が入り口じゃなかったことで、結果的に思い入れが強まったんでしょうね。
白山:北村さんとも、全然ファッションじゃない所で偶然巡り会って、こうやって長くお付き合いをさせていただくことになりましたしね。
北村:多分 、白山とはメガネがなくても付き合っていたんだろうね(笑)。



左: 現在40本ほどのメガネを所有しているという北村さん。この日はその中から思い出深い「白山眼鏡店」のオリジナルモデルや同店でかつてセレクトしていたアイテムを持参してくれた。真ん中の楕円が、今回の対談冒頭でも触れたアンティークの1本。
右: 最近はラウンドのセルフレームモデルがお気に入り。タイドアップ&ジャケットにMA-1を羽織った、トラッドをルーツに持つ北村さんらしいスタイルによく似合う。

長い月日を共にしてきた、北村さんのワードローブたち。右上から時計回りに「PORTER」のトートバッグ、「Borsalino」のハット、「白山眼鏡店」のメガネ、「ELOSEGUI」のベレー帽、「CONVERSEADDICT」のスニーカー、「ORTEGA」のチマヨベスト、タイで購入したインディゴ染めの野良着、「H BAR C」のウェスタンシャツ、フレンチヴィンテージのオーバーオール、「L.L.Bean」のキャンバストート、「TONY LAMA」のウェスタンブーツというラインナップ。真っ赤な「PORTER」のトートバッグは還暦祝いに「吉田カバン」から贈られた非売品で、「HERMÈS 」で使用されているものと同等のレザーを使ったという特別なもの。「ORTEGA」は20年以上前のコロラドで、オーバーオールは35年ほど前にパリの蚤の市で見つけたもの。野良着もタイに渡った際に購入していたりと、ひとつひとつとの出会いにもそれぞれ確かな背景がある。ボロボロになったハンドルをリペアし続けている「L.L.Bean」のトートバッグは本場・メイン州で買った愛着の強い1品で、「カミさんからは捨てなさい!と言われ続けてるけど(笑)、やっぱり捨てられない」とのこと。
PROFILE
北村勝彦
1945年生まれ、大分県出身。その後横浜に移り住み、プレス関連の特殊技術者だった父親の都合で幼少期を米軍基地内で過ごし、アメリカ文化に触れて育つ。高校時代には上野・アメヤ横丁で様々な名品を掘り下げるようになり、そうした経験が高じて30代では創刊時から『POPEYE』の制作に参加。まだ日本では前例がほとんどなかったファッションエディター・スタイリストという仕事を確立し、今日まで活動を続けている。最近は原点に返って、名作家の全集を読み直すのが目下の趣味なのだとか。